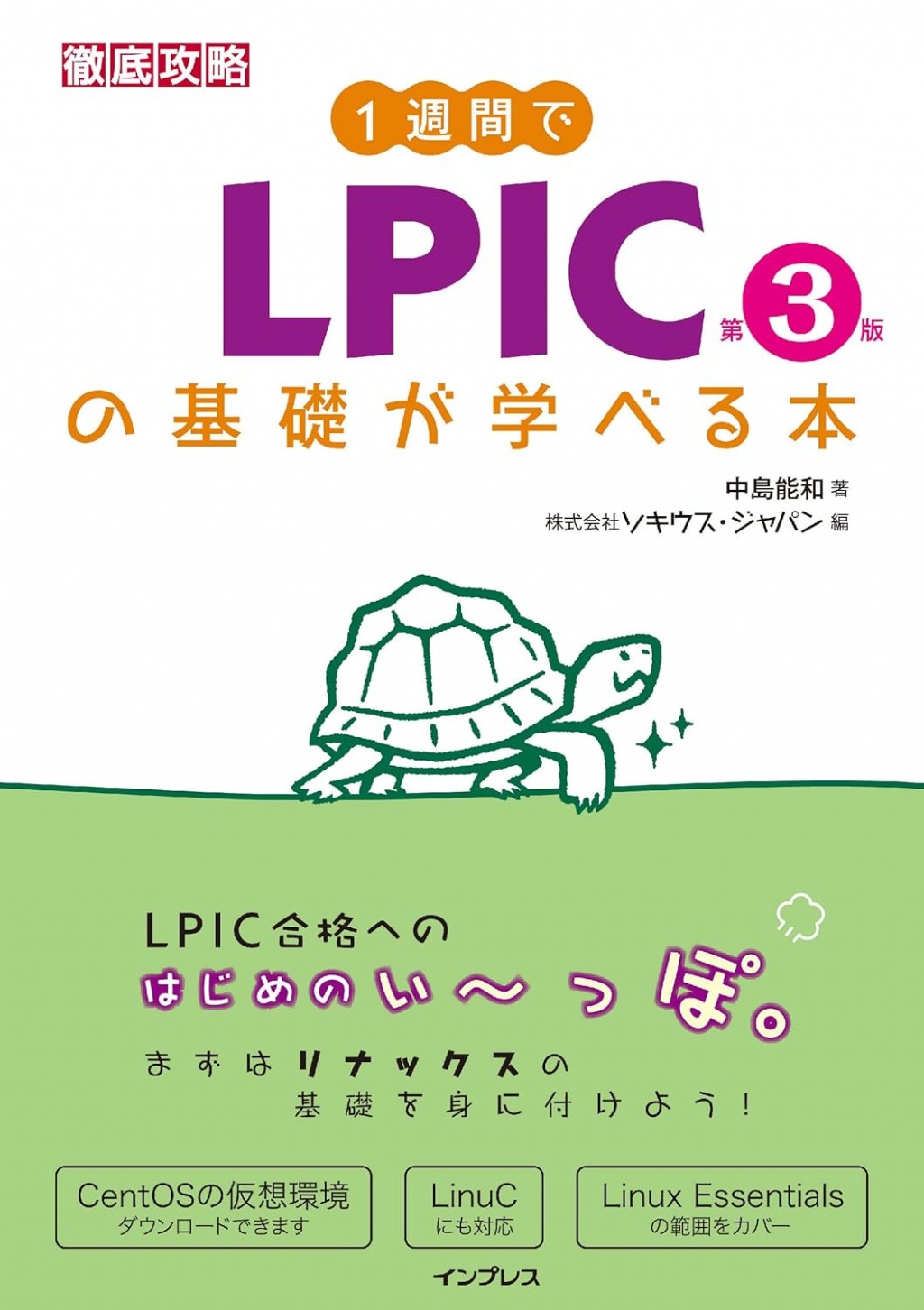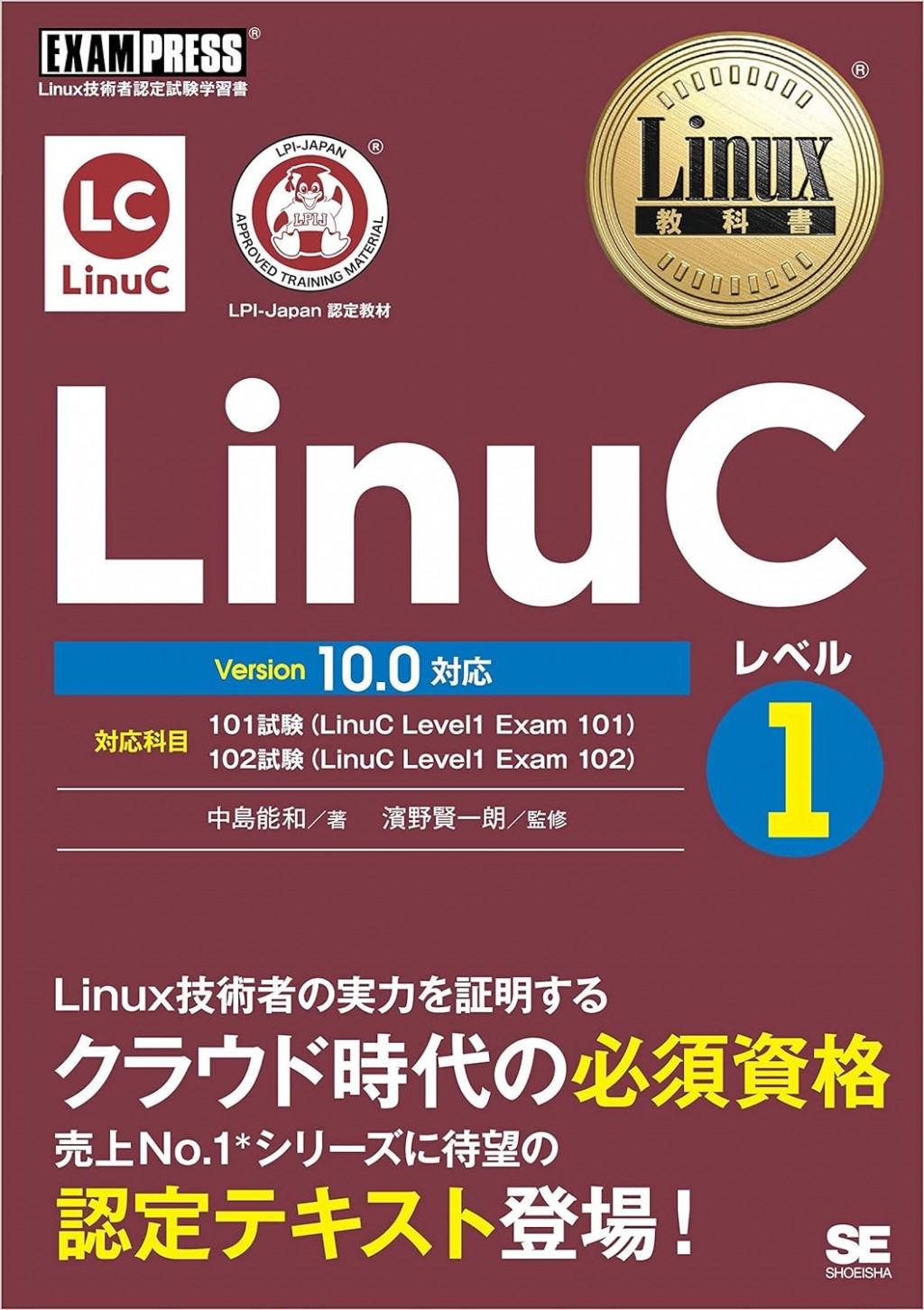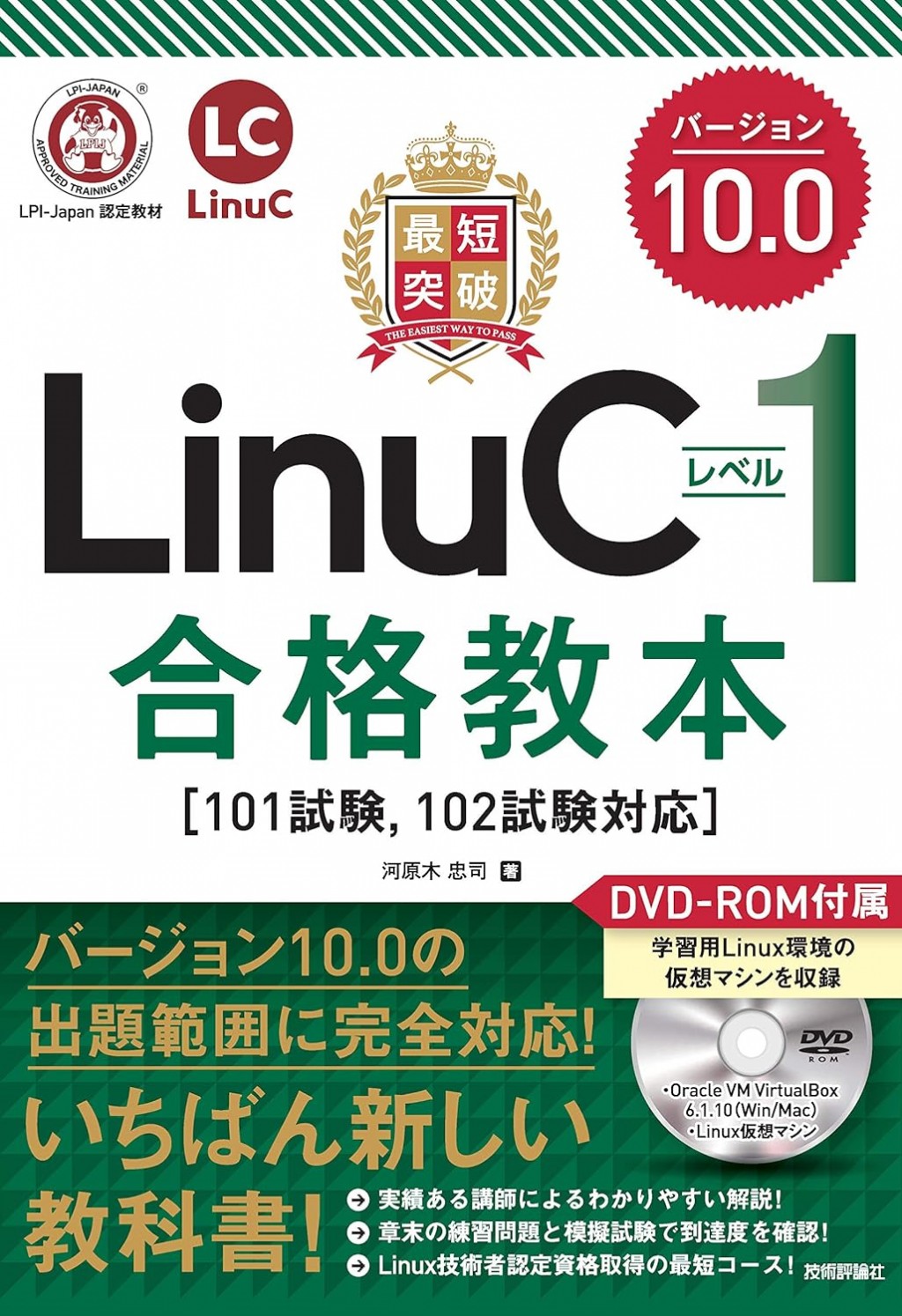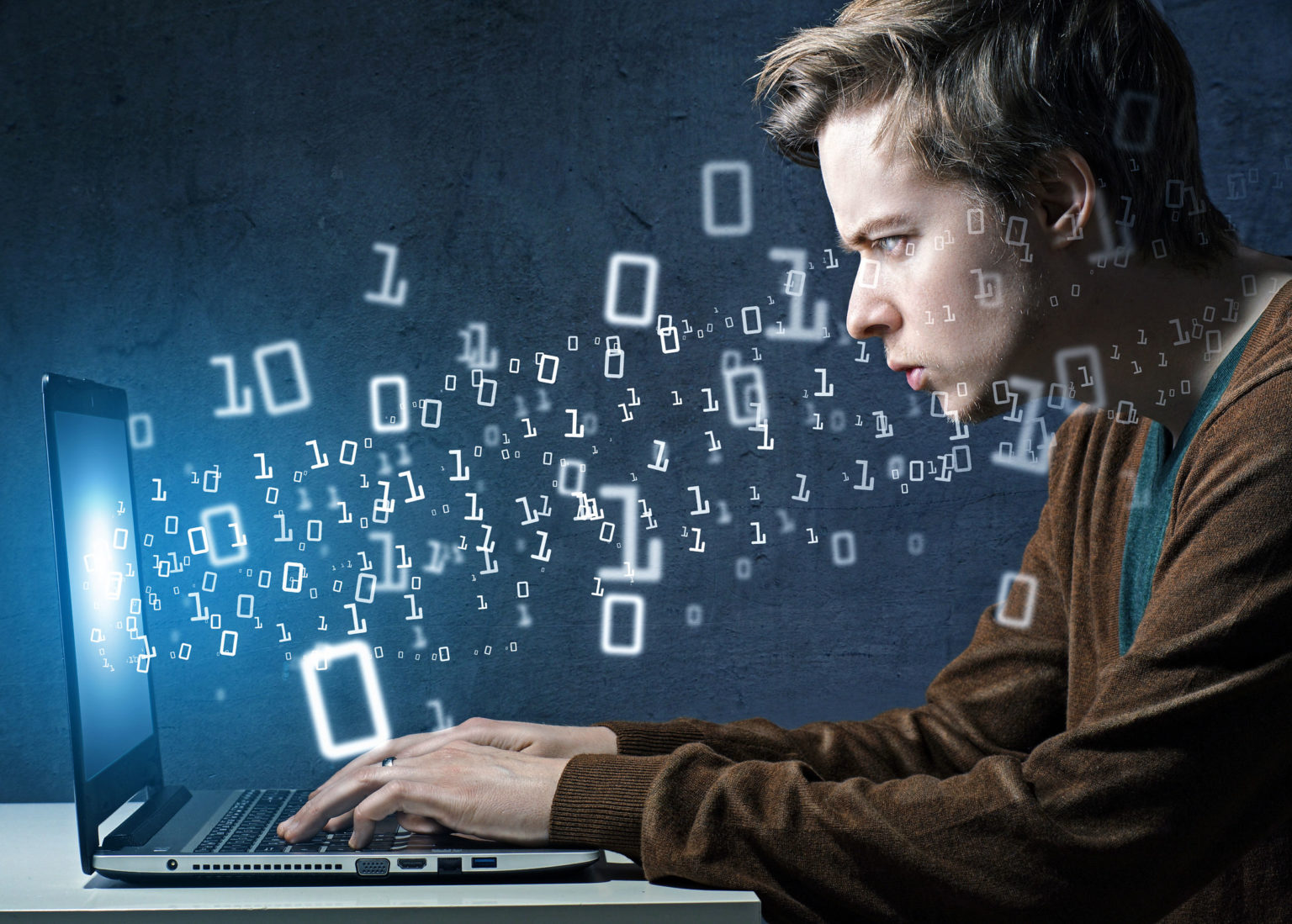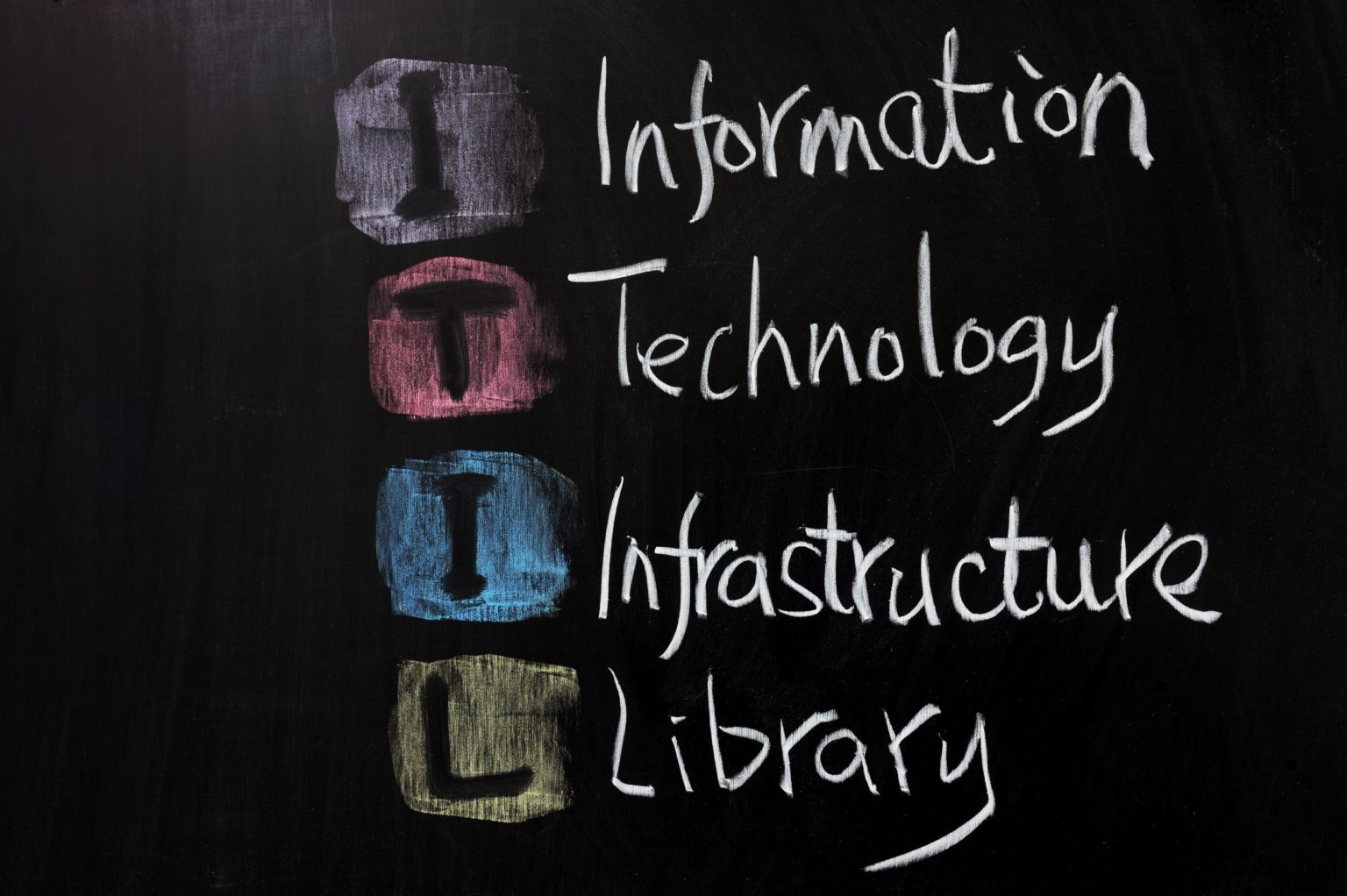LinuCの難易度や試験内容を徹底解説!問題傾向とおすすめの参考書は?LPICとの違いやどっちを受けるべきかも要チェック
Linux技術者認定「LinuC(リナック)」は、2020年の出題範囲の改訂で仮想化/クラウドなどの内容をレベル1とレベル2に取り込み、2023年にはシステム開発の上流工程を担うシステムアーキテクトとしての知識やスキルを問う「LinuCシステムアーキテクト」というレベルの試験をリリースしました。
これによりLinuCはLinuxの運用技術を証明にとどまらず、システム構築や運用管理からアーキテクチャ設計までといった幅広い技術領域をカバーできる資格となり、資格保持者の需要は非常に高いです。
現場やフリーランスとして活躍されている方には、是非取得していただきたい資格です。
しかし、Linux技術者認定として近い存在であるLPICとの違いが分かっていない方も多いのではないでしょうか。
本記事では「LinuC」について、試験の詳細から対策まで詳細に解説しながら、Linuxの資格として有名な「LPIC」とも比較し、どちらの試験を受験すべきか併せて説明します。
LinuC(リナック)とは

Linux技術者認定「LinuC(リナック)」とは、クラウド/DX時代のITエンジニアに求められるシステム構築から運用管理に必要なスキルを証明できる技術者認定です。
習得する技術をLinuxの運用技術にとどめるのではなく、アーキテクチャ設計からシステム構築、運用管理までの技術領域を広くカバーしており、4つのレベルの認定取得を通じて一歩ずつ確実に求められるスキルを習得し、それを証明することができます。
LPI-Japanという特定非営利活動法人により開発・運営されている認定試験で、LPIC(エルピック)を運営しているLPIとは異なる団体です。
LPICとの違いは

実はLinuCとLPICは運営団体が異なります。
LinuCはLPI-Japanが、LPICはLPI-日本支部が運営しており、両社の団体は名前こそ似ているものの全く異なる組織です。
また、LinuCとLPICとでは試験の内容も大きく異なります。
個別の試験の内容についての違いの説明は省略しますが、大きな違いとしては「Linuxの運用技術」を問うのがLPIC、「クラウド利用を前提としたLinuxを含むシステムの開発・運用に必要な技術」を問うのがLinuCということです。
Linuxはご存知の通りオープンソースのOS(オペレーティングシステム)であり、誰でも無料で使うことが出来ます。
結果としてLinuxを基盤として様々なITシステムが世界中で構築・運用されるようになり、システム開発の現場ではLinuxだけでなく仮想化技術、ネットワーク、セキュリティ、オープンソースのライセンスなど様々なテーマについての知識やスキルが求められています。
そのために必要なスキルの保有を証明できる資格として、LinuCが利用されています。
LinuCとLPICはどちらを受験するべきか
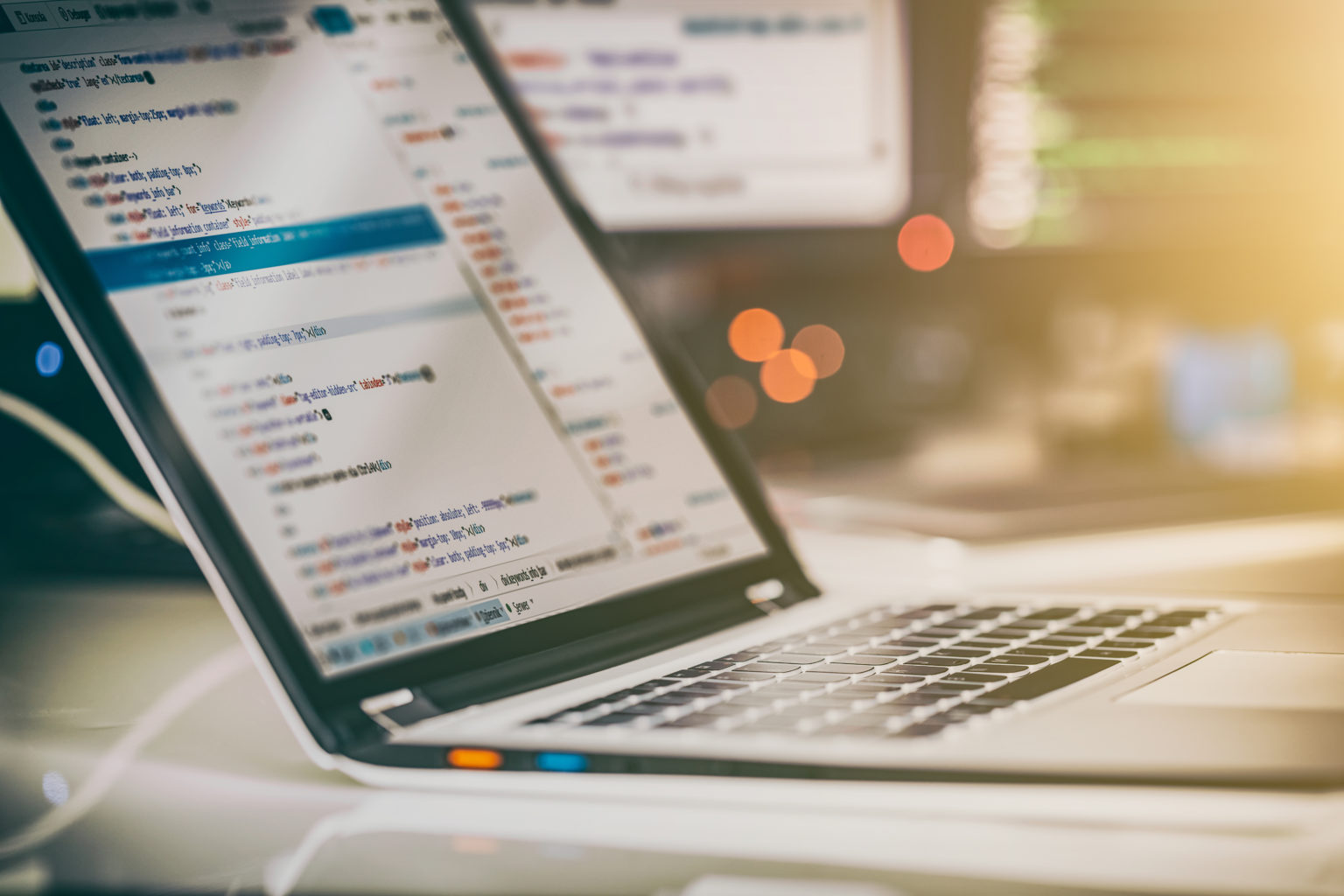
LinuCが作られた目的を考えると、受験すべき試験はLinuCといえます。
LinuCの開発提供の目的の一つに、LPICの問題流出に対応するということがあったからです。
実は数年前からLPICの問題流出が物議を醸しており、流出した解答を丸暗記すれば資格が取れてしまう状態になっています。
この問題流出によりLPICの資格保持者の価値が下がる可能性があります。
LinuCは問題流出に対応する目的で作られた資格であるため、問題管理は徹底されており、資格保持者の価値が下がる心配はありません。
加えてクラウド利用を前提としたLinuxを含むシステムの開発・運用に必要な技術に対応しているので、今後国内での需要や価値は上昇していくでしょう。
ただし、Linuxの内容についてしっかり習得したいと考えている方に関しては、世界共通基準のLPICを受験した方が良いでしょう。
LinuCの試験内容は

LinuCは難易度によって4つのレベルに別れています。
なお、順次ステップアップしていくことを目的にしているため、難易度の低い試験の認定を取得しないと、次のレベルのテストに挑戦することが出来ません。
LinuCレベル1
LinuCレベル1は最も低い難易度で誰でも受験可能です。
資格を取得するためには、101試験/102試験という2つの試験に合格する必要があります。
101試験と102試験は同時に受験する必要は無く、5年以内に両方の資格を取得すれば合格となります。
裏を返せば片方の試験に合格してから5年経過すると、合格の有効性が無くなってしまうのでご注意ください。
公式サイトは、LinuCレベル1について次のようなスキル指標になると説明しています。
-
仮想マシンとコンテナを含むLinuxサーバーの操作と運用管理ができる。
-
クラウドのセキュリティを理解し、安全に運用できる。
-
オープンソースの文化を理解し、業務に活用できる。
Linuxの知識やシステム構築などLinuxの基本的なスキルを裏付けする、IT業界への入口となる資格です。
学習期間は1~3ヶ月とされていますが、実務経験がある方は1か月未満で取得する場合もあります。
しかし、実務経験があっても対策を行わなければ合格は難しいです。
後述しますが受験料が高額なので、経験者でもしっかりと勉強して受験することをおすすめします。
LinuCレベル2
LinuCレベル2は中間の難易度で、受験にはLinuCレベル1の取得が必須です。
LinuCレベル1と同様に201試験/202試験という2つの試験を5年以内に合格する必要があります。
公式サイトでは次のスキルの指標になるとされています。
Linuxシステムの設計、構築、監視、トラブルシューティングができる。
仮想マシンやコンテナの仕組みを理解し、その管理と運用ができる。
セキュリティとシステムアーキテクチャの基本を理解し、サービスの設計、構築、運用・管理ができる。
LinuCレベル2はLinuCレベル1に比べてより実務的な内容になっており、エンジニアとして即戦力になることが裏付けされます。
市場価値やフリーランスとして需要が高まる基準といえるでしょう。
勉強期間は3ヶ月~半年が目安となります。
LinuCレベル3
LinuCレベル3は特定領域のプロフェッショナルであることを証明する資格で、資格の取得にはLinucレベル2の資格取得が必須です。
Linucレベル1、レベル2と異なり、300試験/303試験/304試験の3つの試験の内、1つのテストに合格することでLinucレベル3を取得できます。
もちろん全ての試験を受験することも可能です。
各試験で証明出来るスキルは異なるものの、「各分野の最高レベルの技術力を証明できる」という点は共通しています。
勉強期間の目安は、どの試験においても半年~1年とされています。
全ての試験合格を考えると更に期間を設ける必要があるでしょう。
300試験

複数のOSが混在するシステムに特化した技術力を証明する試験です。
裏付けされるスキルは以下のようになっています。
-
Linux、Windows、UNIXの混在環境でのシステムインテグレーションやトラブルシューティングができる。
-
冗長構成でLDAP、OpenLDAP、Sambaを使ったシステムや認証サーバーを構築できる。
出典元:https://linuc.org/linuc3/300.html
303試験
セキュリティレベルの高いシステムに特化した技術力を証明する試験です。
裏付けされるスキルは以下のようになっています。
-
Linux環境での認証の技術及びシステムセキュリティを考慮したシステム計画、構成、設計、構築、実装ができる。
-
セキュアなシステムにするために、ぜい弱性及びその対策を評価し、トラブルシューティングができる
出典元:https://linuc.org/linuc3/303.html
304試験
クラウドシステムに特化した技術力を証明する試験です。
裏付けされるスキルは以下のようになっています。
-
仮想化の概念と技術を理解し、Linux/OSSを使って仮想化システムを構築、運用する専門家であることを証明できる。
-
負荷分散、クラスタ管理、クラスタストレージなどの高可用性のための技術をLinux/OSSを使って構築、運用できる能力を証明できる
出典元:https://linuc.org/linuc3/304.html
LinuCシステムアーキテクト
LinuCシステムアーキテクトは最高難度の資格で、資格の取得にはLinuCレベル2の資格取得が必須です。
LinuCレベル1やレベル2と同じようにSA01試験/SA02試験の2試験に5年以内に合格する必要があります。
公式サイトでは次のスキルの指標になるとされています。
分散システムの処理構造について、典型的なパターンの特長を理解し使い分けられる。
プラットフォーム/ミドルウェア/ネットワーク/ストレージについて、Linux/OSSによる具体的な構成を決定し構築・設定でき、クラウドサービスの機能を用いたりリソースを動的に確保するなどの構成も必要に応じて選択できる。
非機能要件のそれぞれを実現するための要素技術を理解し、 Linux/OSSにより実践できる。また、クラウドネイティブな設計アプローチや開発手法を理解し、システムに採り入れられる。
安定稼働と継続的開発を見据えた監視やテスト体制を設計し、また運用中のトラブル対応を主導できる。
出典元: https://linuc.org/linucsa/
LinuCシステムアーキテクトは、レベル1からレベル3に比べて個別の技術についての知識について問うのではなく、システム全体を俯瞰してシステム設計・構築をするための能力を問い、それがあることを裏付ける資格です。
システム開発の上流工程を担えるエンジニアとして非常に希少で求められる存在と言えるでしょう。
勉強期間は半年〜1年が目安となります。
LinuCの試験詳細

上述した試験の具体的な受験形式はおおよそ統一されています。
試験時間は90分、問題数はレベル1〜レベル3は約60問/ 1試験、アーキテクトは約40問/ 1試験で合格率は非公開ですが65~75%程度となっています。
出題方法はCBT方式でマウス選択問題が大部分を占めますが、キーボード入力問題も出題されます。
また、受験料はレベル1〜レベル3が一律16,500円(税込)/ 1試験、システムアーキテクトが27,500円(税込)/ 1試験となっています。
またLinuCレベル3の試験のみ、不合格の場合一度だけ5,000円で再受験が可能です。
とはいえ高額であることに変わりないので、しっかりと対策を行ってから受験しましょう。
受験について
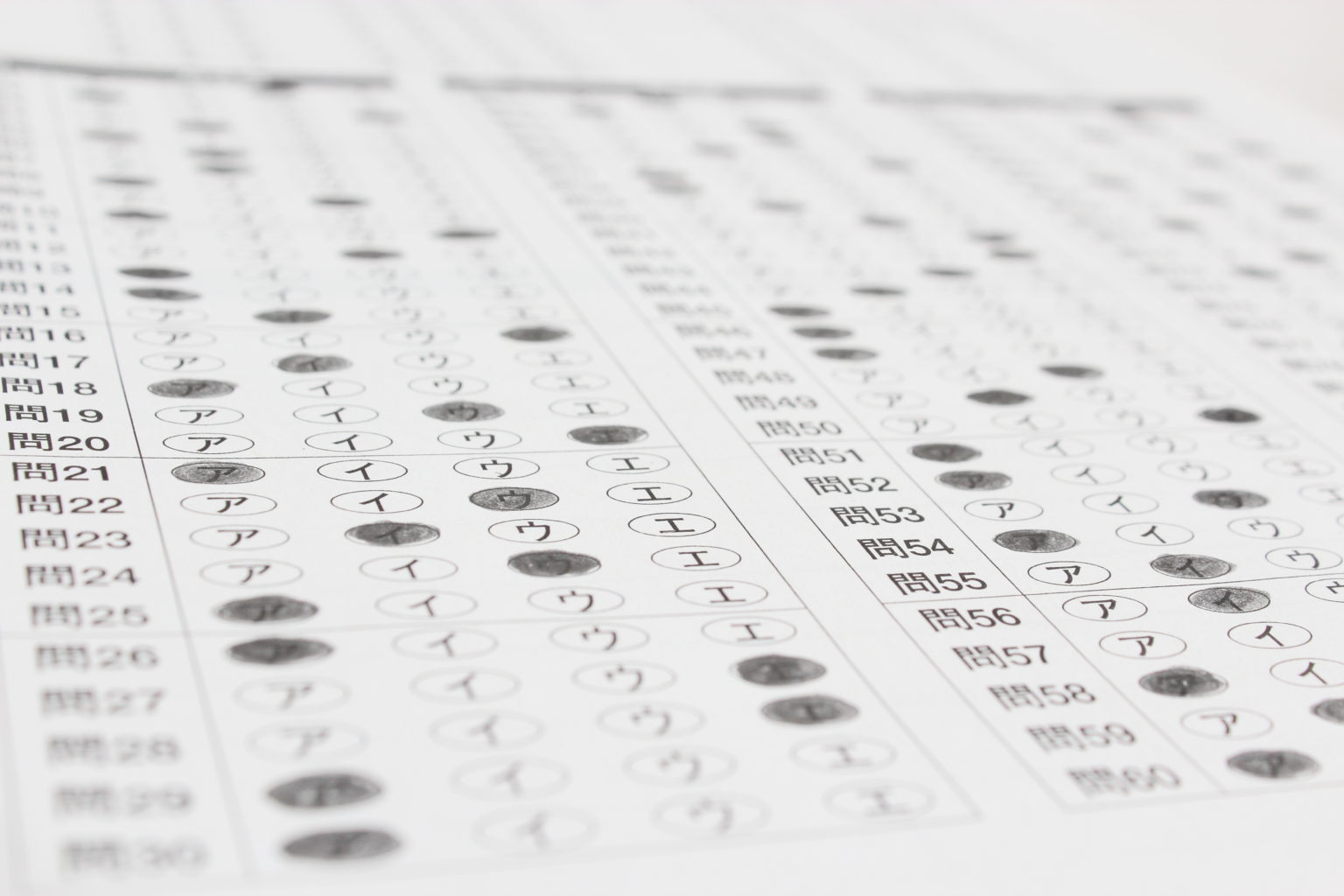
実際の試験の流れを、申し込みから結果を受け取るまで説明します。
なお実際に受験する時は、LinuCの公式ページや予約時に届いたメールをよく確認して下さい。
申し込み
LinuCは全国100か所以上のテストセンターに出向いて受験します。
受験日時は会場として希望するテストセンターの予約の空き状況を踏まえて指定することができます。
申し込む際はバウチャーと呼ばれるLinuC共通受験チケットを購入する必要があります。
バウチャーを購入すると12文字の英数字コードがメールに送られるので、そのコードを用いて受験予約を行います。
なお有効期限は1年間ですのでご注意ください。
会場後
会場についたら本人確認のため、写真撮影と署名の確認を行う必要があります。
本人確認が終わったら私物を全てロッカーに預けて試験室に入室します。
試験が終わったら受付にてスコアレポートを受け取り、無事終了となります。
2020年11月からオンライン受験が可能に
これまでLinuCは会場に出向いて受験しなければなりませんでした。
しかし、2020年11月からはオンライン受験も可能になり、インターネットがあれば自宅や職場で試験を受けることもできるようになったのです。
選び方は簡単で、手続きで「自宅または職場」というオプションを選べばオンライン受験を申し込めます。
試験を予約する前に、システムテストで正常に動くか確認しておくことも大切です。
当日は予約時間の30分前から入れますが、遅刻は厳禁なので注意してください。
オンライン受験の際は、一人になれる部屋で安定したインターネット回線で受けることが条件です。
また、本人確認書類も手元に用意しておきましょう。
オンライン受験が可能になったことにより、会場の場所や空きを気にする必要もなくなりました。
より受験しやすくなったといえるのではないでしょうか。
LinuCを取得するメリット

ここまでLinuCについて解説しましたが、受験料は高額で勉強時間も長期間を要することになります。
ですが、「そこまでの時間と労力を注ぐ価値はあるのか」と疑問に感じる方もいるかもしれません。
ですが、先に結論を申し上げます。
時間と労力を注ぐ価値は十分にあります。
LinuCを取得するメリットを説明します。
試験を通じてスキルアップする
LinuC取得のための勉強は実務やスキルに直結します。
当たり前のように感じるかもしれませんが、意外と資格とスキルは結び付かないことが多いです。
例えば、TOEIC900点の人でも英語を全く話せないなど、日本では資格を肩書としてのみ使用するケースが多いです。
一方でLinuCはスキルが資格と結びついており、実務の中でも勉強したことが役立つように作られています。
実際に資格取得後の満足度は89%と非常に高く、取得することで何かと役に立つ資格だと多くの人が感じるようです。
市場価値が高まる
LinuCの資格保持者の市場価値は非常に高いです。
というのも、LinuxOSを利用している企業は多く需要が拡大している一方で、日本はLinuxに対する初動が遅かったためか、Linux技術者が常に不足している現状があるからです。
加えてLinuCは「クラウド利用を前提としたLinuxを含むシステムの開発・運用に必要な技術力を証明する資格」であるため、今後の需要は右肩上がりで大きく伸びると考えられます。
フリーランスとして活躍している方は、資格を取得することで信頼がさらに大きくなるでしょう。
LinuCの問題傾向と対策
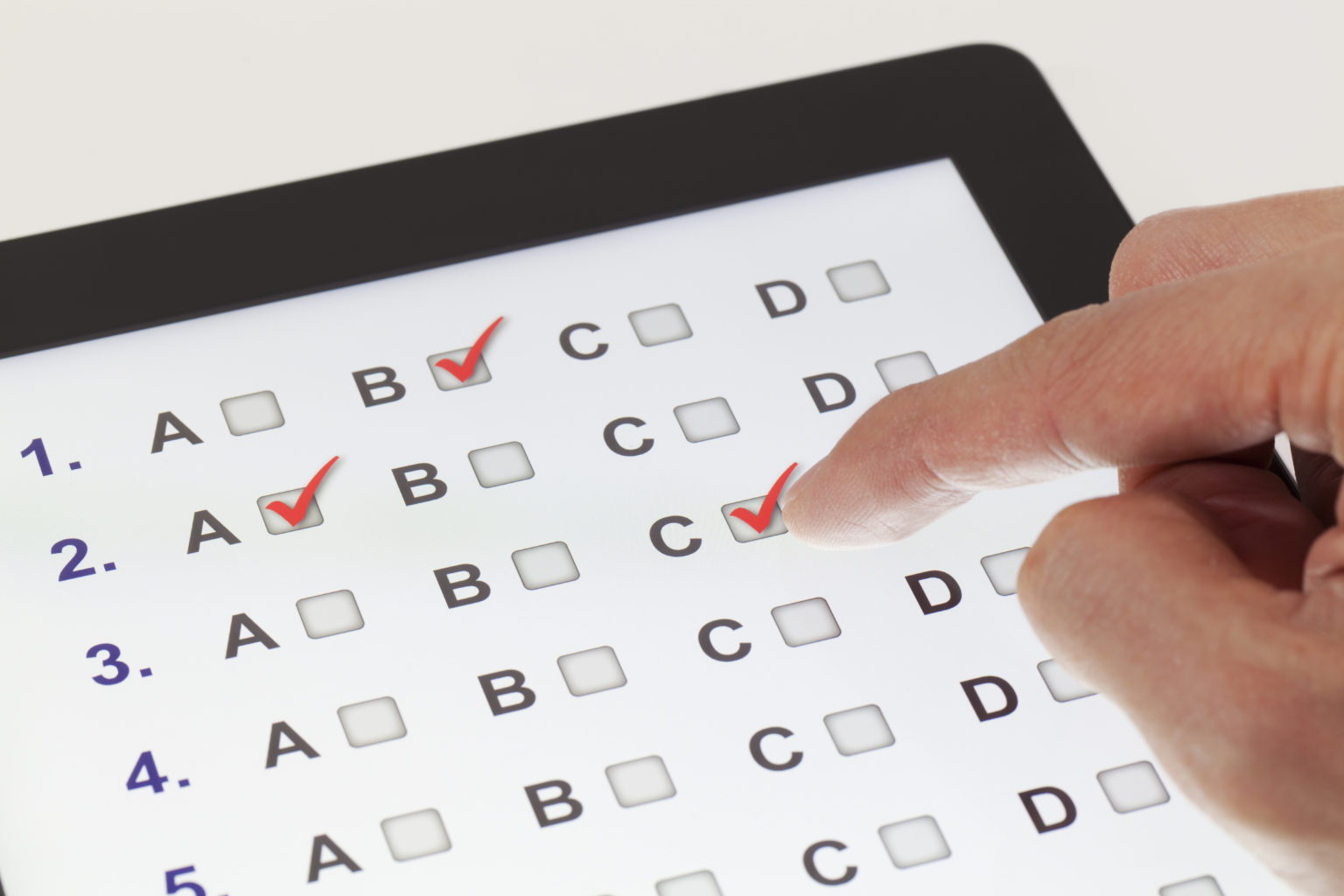
LinuCの問題傾向や対策においては、それぞれの試験の出題範囲をしっかり確認することが大切です。
対策としては、書籍を読むだけでなく、読んだ内容を実際に手を動かして試して確認をしながら進めていく、という方法が良いでしょう。
おすすめの参考書

Linuxに関して基本的な知識がある方や、実務での経験がある方はLPI-Japan認定教材を使って勉強することが最も効率的ですが、初心者の方は認定教材の前にLinuxの基礎を勉強することを強くおすすめしたいです。
それではLinuCの勉強におすすめの参考書を紹介します。
基礎を理解したい人向け(1週間でLPICの基礎が学べる本 第3版 徹底攻略シリーズ)
こちらはテスト対策というよりLinuxの基礎知識を学ぶ参考書です。
この本でLinuxの最低限の知識を得ていないと試験勉強が苦痛になるかと思います。
Linuxの初心者に向けに書かれており、小難しい言葉を使わずに分かりやすくLinuxを理解出来るようになっています。
ただし事前知識がある人には物足りない内容と思われます。
またLinuCの試験範囲を全て網羅していないため、この書籍だけでLinuCを合格することは不可能です。
初心者から中級車への橋掛かりとして使って下さい。
事前知識がある人向け(Linux教科書 LinuCレベル1、Linux教科書 LinuCレベル1 スピードマスター問題集)
Linuxについて最低限の知識がある人は、LPI-Japan認定教材である、Linux教科書 LinuCレベル1(通称あずき本)がおすすめです。
また、以下のLinux教科書 LinuCレベル1 スピードマスター問題集(通称白本)を用いた学習がおすすめです。
二冊とも内容がよくまとまっており、解説も分かりやすく「LinuCを受けるならこの2冊」といっても過言ではない王道の参考書です。
また、あずき本と白本はLinuCレベル2に対応しているものも出版されています。
LinuC対応参考書(最短突破 LinuCレベル1 合格教本 [101試験, 102試験対応] )
レベル1しか発売されていませんが、LinuCレベル1を受験する予定の方は、こちらも選択肢としていかがでしょうか。
勉強法
それでは実際のあずき本と白本の使い方を説明していきます。
まずはあずき本でインプットを行います。
理解して頭に落とし込んでください。
もちろんコマンドなどは暗記するしかありませんが、丸暗記するのではなく語源を調べて納得するようにしましょう。
すぐには覚えられませんが、問題演習を行う際に効果が表れます。
次に白本でアウトプットを行いましょう。
分からない問題もすぐに答えを見ず、何か手掛かりがないか最後まで考えて下さい。
正解を出すことではなく、とにかく考えることが大切です。
このように、ひたすら考えた後に答えを見る瞬間が一番記憶に定着しやすくなります。
この時インプットを全力で行っていれば、答えを見たときのインパクトが大きくなるので、より記憶に定着しやすくなります。
これを繰り返して勉強を行って下さい。
LinuCはエンジニアを目指す人にとって非常におすすめの資格
LinuC資格保持者はこれからも需要が増え続けるでしょう。
また、インフラエンジニアは不況に左右されにくいため、安定性も抜群です。
取得の難易度は高く長期間の勉強も必要ですが、皆さんの市場価値やスキルはさらに高まるはずです。
日本のIT業界では常にエンジニア不足のため、エンジニアはフリーランスやマルチワークで大きく収入を得ることが出来ます。
その1つの手段として、是非LinuCを取得してさらなる活躍を目指してみてはいかがでしょうか。